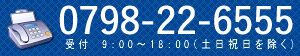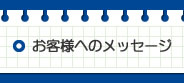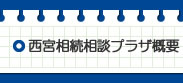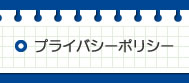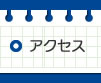相続用語集
あ行
相続用語には普段聞きなれない専門用語が多く使われています。聞きなれない言葉だけにその意味もわからないことが多いかと思います。そんな専門用語をまとめ『相続用語集』を制作しましたのでお知りになりたい用語と意味はこちらでご確認下さい。
【遺産分割】
被相続人が残した財産を、相続人に配分する手続きのことです。遺産を分割する方法は遺言による指定、相続人全員による遺産分割協議、協議で話し合いがつかない場合は家庭裁判所による調停・審判となります。遺産分割は、相続や遺贈によって得た財産から債務・葬式費用を差し引いてから個々の相続人の相続割合を計算します。
【遺贈】
遺言で財産を特定の者に与えることです。特定遺贈と包括遺贈がありますが、通常は財産を誰に遺贈するかが明確な特定遺贈が一般的です。包括遺贈とは全財産を割合によって遺贈する方法で、相続人でない人に相続人と同様の権利義務を与える方法をいいます。なお特定遺贈により財産を取得した人が法定相続人である場合とない場合では、相続税の負担に違いがあるので注意してください。
【遺族基礎年金】
国民年金加入中の人や国民年金の保険料を払い終わった60歳以上65歳未満の国内に住んでいる人が亡くなった場合に18歳未満の子をもつ妻や両親のいない18歳未満の子などに支給される年金のことです。
【遺族共済年金】
共済年金保険に加入中の人や共済年金の加入をやめたあと共済年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で初診日から5年以内に亡くなった時などに支給される年金のことです。
【遺族厚生年金】
厚生年金保険に加入中の人や厚生年金の加入をやめたあと厚生年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で初診日から5年以内に亡くなった時などに支給される年金のことです。
【遺留分減殺請求】
相続財産から贈与や遺贈を差し引いた時に、遺留分の額に達しない場合、遺留分権利者やその承継人が遺留分を保全するために、贈与や遺贈の履行を拒絶することです(給付済み財産については返還請求)。
か行
【寡婦年金】
国民年金加入中の人が亡くなった場合に遺族基礎年金の支給条件に合わない妻に対し夫が生きていればもらえたはずの老齢基礎年金の4分の3に相当する額として支給される年金のことです。
【居住用財産の譲渡】
2004年から土地建物についての損益通算・繰越控除が廃止となりましたが、居住用不動産については特例が設けられています。特例としては3,000万円特別控除、長期譲渡所得の課税特例、損失の繰越控除、買換え等の譲渡損失繰越控除などです。
【公証人】
30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員のことです。公証役場一覧表記載の公証役場で執務しており、公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行います。
【公正証書】
公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
【更正の請求(国税通則法)】
申告によって確定した課税標準または税額を、納税義務者が自己に有利に変更するように税務署に求める手続きのことです。税額などを変更するという点では修正申告と同じですが、修正申告が自主申告によって変更するのとは異なり、税務署の更正権限の行使によって変更されます。更正の請求は、所定の事項を記載した更正請求書を税務署に提出して行います。
さ行
【債務控除】
相続税の計算の際に、取得財産から引く債務・葬式費用のことです。
【事業承継】
被相続人が事業を行っていた場合、その事業を後継者に引き継ぐことをいいます。
【死亡一時金】
国民年金を3年以上納めている加入者が、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに亡くなり、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族がいないときに支給される給付金のことです。国民年金の保険料を納めた期間で支給額が決まります。
【借地権】
建物の所有を目的とする地上権または土地の貸借権のことです。地上権は土地を専用に使用する権利のことで、主に居住が目的であれば、建設、登記、売買することもできます。賃借権は地主に賃料を払い土地を借りる権利で賃借権を譲渡、転貸するには地主の承諾が必要です。
【住宅取得資金の贈与税特例】
住宅取得資金を親などから子などに贈与した場合の贈与税の特例として、暦年課税の特例(5分5乗方式)がありましたが、2006年度の法改正で暦年課税の特例が廃止され、2006年1月1日以降は相続時精算課税の特例のみとなっています。
【小規模宅地等の特例】
被相続人が居住用・事業用に使っていた宅地で一定の要件を満たせば、居住用で最大240平米まで80%減額、事業用で最大400平米まで80%減額になる制度です。
【成年後見制度】
認知症、知的障害などの理由で判断能力が不十分になると不動産や預貯金などの財産を管理したり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分で処理することが難しい場合があります。その時のために財産管理や医療契約、施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わって仕事してくれる人(任意後見人)を定めて支援してもらう制度です。
【葬祭費(埋葬料)】
葬儀を行った人が健康保険から費用の補助として受け取れる給付金のことです。申告制で、期限は国民健康保険、社会健康保険ともに加入者が亡くなった日から2年以内になっています。
【相続分皆無証明書】
被相続人から生前贈与などを受けた相続人が「自分が譲り受ける財産はもうない」ということを証明する書類のことです。特別受益証明書、相続分なきことの証明書とも呼ばれています。しかしこの方法は遺産分割協議手続や相続放棄手続の脱法手段として濫用される危険性があり、紛争のもとになりやすいとの批判があります。
【相続財産法人】
被相続人の死後、相続人がいない場合、民法の規定で法人格が与えられる財産のことです。利害関係人や検察官の申し立てにより家庭裁判所が選任した相続財産管理人が管理します。
【相続登記】
不動産の所有者が死亡すると、相続人に所有権が移転するためひつような不動産の名義変更手続きのことです。相続登記を行わないと、固定資産税は被相続人の名義でかかる上、不動産を売ることはできません。
た行
【特定事業用資産の特例】
要件を満たす自社株や特定の立木等について一定の負担軽減がある制度のことです。
【認知】
嫡出でない子について、その父または母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示を認知といいます。父親が認知しなければ非嫡出子は相続人になれません。認知には父が父の意思で自分の子として認める任意認知と裁判により認知を求める強制認知の2種類があります。
は行
現在ありません。
ま行
現在ありません。
や行
【遺言執行者】
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言書の内容を実現させるために、「相続財産の管理・財産分割」などを行う者のことです。遺言執行に必要な一切の行為をする権利をもち、単独で遺言の執行を行うことができます。
ら行
【連帯納付制度】
相続税・贈与税について自分が納税していても、他の相続人が納税しないと、その分も負担して納税する必要がある制度のことです。過去に裁判でこの制度の可否が争われていますが国側勝訴の判例が出ており、現在でも税金を払うことになっています。また日本税理士会連合会と日本弁護士連合会が共同して廃止を求める意見を表明するなど問題になっています。
わ行
現在ありません。